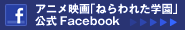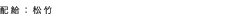[『ねらわれた学園』特別対談]中村亮介 × 氷川竜介 第ニ回
今の時代とあの年代を物語るテーマ
恋愛というコミュニケーション
氷川:今回のオリジナルの物語というのは、再度原作を読まれて考えたんですか?
中村:そうです。原作にはいつも、敬意をもって接したいというのが僕の気持ちでして。とうぜん設定としては変更する部分もあるわけですけど、それは原作の魅力を一番いいかたちで今伝える為にはどうするか、アニメという媒体で伝える為にはどうするか、ということだと思っているんです。原作に忠実であるというよりも、誠実に――と。コミュニケーションを今回の映画のテーマにすることや、アイテムとしては携帯にフォーカスすることは、サンライズの平山(理志・プロデューサー)君が、最初の打ち合わせでアイデア出ししてくれたことで、僕もなるほどと思いまして。たしかに何度も映像化されてる名作ですから、また同じ切り口で見せるならば、そちらを見てもらえればいいわけですよね。わざわざアニメにする必要もない。それなら、なぜ「今」、なぜ「アニメ」で、この映画を作るのか。その意味がはっきりした映画でありたいと思いました。コミュニケーション――ほかの言葉にすると「絆」とか「繋がり」とかですけど。それは今の時代の大きなテーマですし、主人公である中学生たちは、ちょうど人生の中で最初にそうした問題にぶつかる年代でもあると思う。原作のテーマはファシズムですけど、そうした原作が書かれた時代背景のテーマを、現代のテーマに置き換えることで、原作の魅力を一層引き出せるんじゃないかと思ったんです。
氷川:シナリオがものすごく練り込まれていて、〈伝わる・伝わらない〉ということをセリフの言葉の中にかなり織り込んでますが、やっぱりそういう部分を中心にしようと?
中村:はい。ただ、コミュニケーションってだけだとすごく抽象的なテーマで。いきなりそんな話をされたって、観てて面白い人なんていませんよね。それを誰にとっても経験のあるストーリーに具体化することで、コミュニケーションというテーマを身近に感じてもらう必要があって。その入り口にふさわしい題材といったら、やっぱり恋愛だろうと。伝えたいのに伝わらない思い、知りたいのにわからない相手の気持ちに悩んだことが、誰しも一度はあるはずだろうと思いますから。
氷川:恋愛は恋愛でも、ちょっとラブコメタッチなんですよね(笑)。マッドハウスにいらっしゃったから、割りと硬派なものが好きなのかと思ったんですが(笑)。
中村:人がどんどん死んでいくハードな作品よりも、個人的には、実はそういうハートウォーミングでユーモアのある物語のほうが好みなんですよね(笑)。
中学時代を描くに当たって触発された、
アンジェラ・アキの楽曲とドキュメンタリー
氷川:主人公のケンジとナツキはお隣さんというすごく王道の設定で、まさに部屋の窓が向かい合っているという関係ですよね。
中村:そこはわかりやすくと言いますか。ナツキは人間関係上、いわゆるガール・ネクスト・ドア(=親しみやすい近所の女の子)という立ち位置ですけど、本当に家も隣のほうがそれがわかりやすいかなと。ケンジにとって、すごく身体的な距離の近い女の子ですね。カホリはその逆で、距離の遠い憧れの女の子という立ち位置です。
氷川:そこに京極を入れて、三角関係じゃなく四角関係にするというのも、最初から考えられてたんですか? 四者四様のもつれ方が、すごく面白いなと。
中村:それも最初からですね。原作はもっと超能力にフォーカスした物語で。僕もプロット段階では、原作に準じて超能力をめぐる権力闘争の話が多かったんですよ。でも、今回の映画のテーマはコミュニケーションなので。彼らメインの4人の間関係や、心情の繊細な変化を丁寧に追うことが、結局は今回の映画を描くことなんだなと思って。
氷川:作品を作りながら、中学時代のことは結構思い出されたりしたんですか?
中村:思い出しましたね、自分のバカなこととかたくさん(笑)。それから、アンジェラ・アキさんが中学生の合唱コンクールのために作った『手紙~拝啓 十五の君へ~』っていう曲にちなんだ、『拝啓 十五の君へ』っていうNHKのドキュメンタリー番組があるんですよ。アンジェラさんが15歳の時に30歳の自分に宛てに書いた手紙があって。本人も忘れていたんですけど30歳になった時にお母さんから渡されて、15年越しに自分に手紙が届くんですね。それで手紙を読むと15歳の自分は、今の自分から見たら、とても些細なことで真剣に悩んでるんですよ。
氷川:中学生の頃って、そういうものですよね。
中学生は思ったより考えていて、思ったよりバカ?
過去の積み重ねが現在に繋がっているということ
中村:ただ、中学生の自分はそこですごく悩んだことも、自分にとってのリアルなんですよ。その実感にたいして、大人になった今の自分が、そんな悩みは些細なことだよって言うことは絶対できない。言えることがあるとしたら、「大丈夫だから」って言うことしかない。そういう内容のドキュメンタリーだったんです。確かに中学生の頃って、学校と家と通学路だけが世界のすべてで。その中で切実に悩んで、一生懸命生きてたんですよね。あらためてそれを思い出して。この映画も、子供の悩みを大人の目線から見て、それは小さなことだと言ってしまう映画にはしたくなかった。それをずっと作品の背骨として、意識し続けていました。
氷川:過去の愚かさを否定するんじゃなくて、そのよさを見出すこと、その積み重ねが今を作っているって認識するっていうことは、未来が過去を変えようとするこの作品のテーマ自体とも重なってくるとこですよね。
中村:まさにそうですね。未来の目線から過去を正す、と安直にしてしまう考え方の、雑さといいますか。人が生きているのは「今」だけで、愚かなこともそうでないことも、その積み重ねだけが降り積もって、未来があるんだと思うんです。作品づくりもそうで。ひとつひとつ、一歩一歩、小さなことを積み重ねていった結果、今、こういう形の映画ができあがっているんだと思うんです。自分という人間も、この世界も、きっと同じなんだろうと思うんですよ。
第三回へ続く